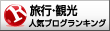旧田中家住宅の続きです。
3階のもう一つの部屋は来客用の「大広間」は、これまたゴージャスなお部屋。ゲストを迎え入れる応接室はたいてい1階にあるものですが、建主のこだわり炸裂!見晴らしの良い3階にあるんです。
 3階 大広間は超ゴージャスな応接室
3階 大広間は超ゴージャスな応接室
前回紹介した「控えの間」からは廊下に出ずにお客様を迎え入れる大広間へ行くことができます。
控えの間にある白いドアを開けると、

裏側は茶色いドア。控えの間の白で統一されたお部屋とは異なり、重厚な部屋として装飾されていました。

先がくるくるっと丸まったイオニア式オーダーの柱!
おいおい、外の装飾でなくて、家の中にこんな柱を作っちまったのか!![]() これだけでも十分驚きだったんだけど、それが2本ずつのセットになっている。下がっているランプも街灯のようで、室内なのに屋外な感じ。
これだけでも十分驚きだったんだけど、それが2本ずつのセットになっている。下がっているランプも街灯のようで、室内なのに屋外な感じ。

2本の柱が両サイドにあるのには秘密が。この真下は二間続きで柱が建っている和室でして、和室の間取りの通りに柱を建てることもできましたが、中間部分には柱を立てず、大きく開けるために脇に両サイドに2本ずつ柱を建てたそうです。
強度を保つためには必要なことだけど、おかげで控えの間から通じるドアから入ってきた時に、通路を通っているようにむしろ演出ができている。素晴らしい![]() 。
。
通常、応接スペースは1階に作られることが多いですが、眺望が良いということから大広間は3階に設けられました。窓からは岩槻街道を眺めることができるし、当時は高い建物はなく、広い敷地と河岸まで見渡せて、さぞ自慢の眺めだったことでしょう。晴れた日には富士山も見えたそうです!

かつては皇族の方もいらっしゃったという。
やんごとなき方々をお迎えできるほどに、椅子やテーブル、その他の調度品も含めて素敵なんです。
特にテーブル!これもまた天板は大理石???
大きなテーブルを作るのではなく、小さなテーブルが3つ。お客様の人数に合わせて使い勝手が良さそうです。

漆喰の天井の装飾、照明も素敵なデザインです。

右奥への扉は階段室のバルコニーのようなところに出るためのものと思われます。どんな使われ方をしたのでしょうね。

ものすごい広いわけではないけど装飾豊かな大広間を後にします。次は二階へ。
階段を降りると正面にあるのは書斎です。

書斎はあえて、あとまわし。まずは内蔵を探検です。
 2階 内蔵で旧田中家について学ぶ
2階 内蔵で旧田中家について学ぶ

3階とは異なり、数段の階段を上って入ります。
2階の内蔵は、近年は居間として使用されていたそうです。内蔵とはいえ窓があるので自然光が入ってくる。とはいえ、やっぱり居間にしては暗いかな。

2階はこの洋館の建て主、四代目田中徳兵衛氏と田中家住宅の建築の歴史についての展示です。
設計者である櫻井忍夫についてはネットを調べてもあまり資料が無く、展示からいろいろ知ることができました。

旧田中家住宅は4代目田中徳兵衛が大正12年(1923)に建てられました。材木商だったことから木材にこだわり、当時としては最高級の木材を使用し、レンガも職人に1枚ずつ焼かせたそうです。
現在の洋館は火災で一部を残して消失。再建の際に棟札が見つかり、そこに書かれた関係者の名前から、川口市の地元の大工や職人を登用したことが判明したそうです。
田中徳兵衛氏、地元に貢献しているなぁ![]() 。たたき上げで設計者になった櫻井氏によるこだわりでもあったのかもしれません。
。たたき上げで設計者になった櫻井氏によるこだわりでもあったのかもしれません。
和館の棟札には「設計建築技手 府場洋二」とあり、櫻井建築事務所の技術者だったそうです。櫻井氏はすでに亡くなっていましたが、洋館、和館ともに同じ建築事務所によって手掛けられたことにより、違和感なく、そしてハイカラで洒脱な建物に仕上がったのかもしれません。
建築費用の総額は18万円。現在の金額でいうと2億5,000万円!![]()
でも、当時は川口の地価はさほど高くなかっただろうし、3階建てでこの広さ、そしてこのこだわり具合を考えると、意外と安い???![]()
江戸時代から材木問屋、味噌醸造で財を成した田中家ですが、東京のベッドタウンとして宅地化が進むにつれ、敷地内での味噌醸造は昭和35年(1960)に終了し、味噌問屋としてリニューアル。それまであった味噌蔵などを取り壊して庭園と茶室が作られ、田中家住宅は接待所としての役割が強くなりました。
平成17年(2005年)に六代目田中徳兵衛が亡くなると、文化財としての高い価値が評価されて川口市が住宅を取得し、翌年に一般公開が始まりました。
平成18年(2006年)に国の登録有形文化財、平成30年(2018年)に川口市初となる重要文化財になりました。
この内蔵には3階同様、内部にまたドアがあったのですがここから先は立ち入ることはできなかったので、内蔵の探検はここまで。階段正面の書斎へ移動します。
 2階 こぶりだけど重厚な書斎へ
2階 こぶりだけど重厚な書斎へ
主人の書斎として使用された部屋です。
腰壁には杉板が貼られていて重厚感がある。3階の控えの間とは同じ造りなのに全く別の部屋のようです。

ワタシが訪ねた7月上旬は、田中家に伝わる五月人形が展示中でした。(通常は5月頃の公開ですが、コロナ期は公開ができず、時期をずらしての公開でした。)
スタッフの方が教えてくれましたが、中央にある木彫りは、桃太郎のお付きの猿、キジ、犬が一枚板から彫られているそうです。確かに、継ぎ目がない。ぐるってカーブしているのがすごい技術だ。
旗をつっている棒もすごい価値があるに違いない。キラキラしているのがわかります?
螺鈿細工のようです。近くで見ると独特のひかり方をしていてきれいでした。

書斎ということであまり大きな部屋ではないですが、天井も力を抜いてない!
和室で格式の高い折上げ天井に白漆喰の壁。そこから下がるシーリングライトも素敵なのです。
本館はまだまだ見どころがいっぱい。これぞ和洋折衷住宅の真骨頂!
本館和室編へ続く
![]()
「和洋折衷のいいとこ取り!旧田中家住宅 INDEX
- (1)和洋折衷 とにかく凝った洋館なのです
- (2)素敵な階段室から3階の内蔵と控えの間へ
- (3)超ゴージャスな大広間は必見!
- (4)和洋折衷を体感するなら和室を見よう!
- (5)池泉回遊式庭園と茶室を見学
![]()
ぽちっとひと押し。応援お願いします♪