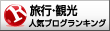埼玉県川口市の大通りに突然現れる3階建ての「旧田中家住宅」は、外観のイメージとは異なり、内部には和室もあり、「変わっている」と思うところが意外と利にかなっている驚きの洋館なんです。
東京から近いこともあり、ドラマのロケ地にもよくなっていて、「家政婦のミタゾノ」の「むすび家政婦紹介所」になっていたことも!
国の重要文化財に川口市としては初めて認定されたということもあり、これから観光客が増えてくると思います。ミタゾノだけでなく、昭和初期から中期を舞台としたゴシックホラー系のドラマ(「犬上家の一族」)のロケ地にも使われているので、行けば「見たことある!」と気がつくかもしれません。
訪ねた時は和館は貸し切りイベントがあっては入れなかったので、大正期に建てられた洋館をレポします。
昭和期に建てられた和館はいずれまた。
(でも洋館なのに和室もあるこの不思議さ・・・。)
 1.旧田中家住宅とは?
1.旧田中家住宅とは?

埼玉県川口市の旧田中家住宅がある周辺は、江戸時代から豊かな地下水と麦を使った味噌づくりが盛んだったそうです。川口と言えば映画「キューポラのある街」で有名な鋳物生産の町だと思っていたけど、味噌が特産物だったとは驚き。ここで作られた味噌は水運を使って江戸にも運びやすかったでしょうね。
材木商と味噌づくりで財を成した田中家が明治に建てたのがこの旧田中家住宅。
「住む家」兼「接待所」も兼ねた外観の質感とは異なり、内部はゴージャスな建物です。
田中家は代々「田中徳兵衛」と名乗り、この建物は4代目徳兵衛が大正12年(1923)に建てられたレンガ造りの3階建ての洋館と、昭和9年(1934)に増築された和館から成り立っているのですが、その建物をかつてはぐるっと味噌蔵が囲んでいました。
洋館の構造は「木造煉瓦構造」といって、埼玉県内の住宅としては唯一の建築物。一般住宅としては珍しい構造で、レンガで覆われていることから耐火性も抜群だし、デザイン性にも優れています。
近くには芝川が流れ、敷地内に河岸があった田中家はそこから材木を各地に運んでいきました。敷地内に河岸があるなんて、それだけでも「豪商」の規模がわかる!芝川からは荒川にも出られるし、旧田中家住宅の目の前の車がびゅんびゅん通る国道はかつての岩槻街道(日光御成道)で、陸運も良し。江戸・東京に近いこの場所で産業が発達したのは当然のことだったのでしょうね。
後に味噌づくりは終えて問屋さんへ転身。味噌蔵跡には池泉回遊式庭園が造られました。文庫蔵もまだ残り、敷地面積は2450平方メートル! まわりは宅地開発されてマンションが立ち並んでいますが、旧田中家住宅のまわりだけ大正時代から時が止まったようなのです。
 2.旧田中家住宅 設計者 櫻井忍夫
2.旧田中家住宅 設計者 櫻井忍夫
設計は櫻井忍夫(1863~1926)。学校で正当な建築の勉強をしておらず、現場からのたたき上げで設計者になったのだそうです。大工として修業を積んだ後は佐立七治郎の事務所に入り、本格的な洋風建築を学びました。佐立はジョサイア・コンドルの一番弟子だったので、当時としては最先端の技術を学んだわけです。櫻井が和風建築、洋風建築の両方に精通している、というのも納得。
櫻井が独立して自身の事務所を構えて初めての仕事が田中邸の設計だったということですが、完成したのが1923年。その3年後の1926年に亡くなったというので、もっと長生きしていたら田中邸のような和と洋の建築を活かした彼独特のセンスの建物を設計していったのだろうなぁと思うとちょっとだけ残念です。
- 櫻井忍夫(さくらい しのぶ) 幕末生まれ 1863~1926
田中邸は大正10年(1921)に独立し、建築事務所を立ち上げてから初めての仕事。
田中邸は1921年に上棟、1923年に竣工したが、櫻井は1926年に亡くなっている。
 3.旧田中家住宅のみどころ
3.旧田中家住宅のみどころ
ぜひここは見てもらいたい!というすすめポイントをご紹介。
忘れずにチェックしてくださいね!
- エントランス上部の「TANAKA」のプレート
大正時代にこれが「田中」であると来客者はわかっただろうか!? - 埼玉県では唯一の「木造レンガ造3階建て」という珍しい館
- 1F 応接室横のステンドグラス
この建物には珍しい。おそらく残っているのはここだけ!? - 男性的な 1F 応接室と女性的な 3F 控えの間
あなたはどちらがお好み?
 4.旧田中家住宅 エントランス
4.旧田中家住宅 エントランス

旧田中家住宅はいろんな様式が採用されているそうです。この写真の窓の下にある「凹」のような装飾は、ルネッサンスの影響だったりしますが、一番大きな影響はゼセッションだそうです。百年名家というBSの番組で説明されていて、初めて聞きました!
ゼッセッション
19世紀末にウィーンで起きた芸術運動で、幾何学的なモダンデザインを特徴としています。
凹の装飾だけでなく、最上部にも幾何学的な模様が。
そして一番すごいなと思ったのが、入口の上にある「クリーム色のプレート内にある「TANAKA」の文字。写真だとわかりにくいですが、ばっちり「TANAKA」と彫られていて、そのまわりにもゼセッションの幾何学的な模様が。
なんてハイカラなんだ!ローマ字ですよ!![]()
しかもこんなに大きく目立つ場所に!
完成した1923年にいったい何人がこれが「田中」だと認識できたであろうか!
これって、日本でいう「表札」だよね?なんて大胆なんだ!
外壁を眺めていて気付くのは、レンガであってレンガでない!?光沢があるよう見える。
これは、通常よりも高温に焼くことによってこの質感を出すことができるんだそうです。「焼き過ぎ煉瓦」と呼ぶのだそう。遠くから見たらレンガだとわからないなぁ。
どんな洋館なんだろうと心躍らせて玄関を入ってみると
出迎えたのは畳敷きの帳場だった・・・。![]()
え?入ってきたのは洋館だよね???![]()
いやぁ。不思議な作りです。
この日はコロナ対策もあり、検温や「どこから来たか?」の調査などがあってスタッフさんが詰めていたので写真は撮れなかったのですが、よくある江戸時代の商家の帳場でした。外観とのギャップがすごい!
とはいえ、お客様を迎える最初の場所であるわけで、天井は格天井。まぁまぁな格式の高さです。
玄関からの導線はすでに工夫があっておもしろい。ふつうは玄関から入ってきたら履き物を脱いで帳場に上がるのでしょうが、玄関からすぐ左にドアがあって、履き物を脱がなくても応接室に入れるんです。

応接室は小ぶりなのですが、それでもまぁ豪勢なこと。細かい細工が美しい床から天井まで、手がかかっている。
そして「材木商」だったというだけであって、使っている木の色合いがとてもいい!良い木を使ってるんだろうなぁ。
壁の下のほう、いわゆる腰壁にまで木材が使われていて、なんともゴージャスな雰囲気を醸し出しています。

上を見ると照明に気をとられがちですが、格天井じゃないですか!
洋風の部屋なのに天井は和室の格式の高さを表現しているのね。
と思ったら、ちょっと待て。それどころじゃないぞ。![]()

天井が和の格天井と洋風の白漆喰の装飾!
すごい。こんな天井見たことないぞ!![]()
これは思いつかない・・・。よく組み合わせたな!
かなり異色なコラボだけど、まったく浮いてないぞ。違和感なくしっくりきてる。
旧田中家住宅は時代としては大正時代なので擬洋風建築というわけではないのですが、和風建築、洋風建築の両方に精通している方が設計しているため、こういう和と洋がうまく組み合わさった工夫がいたるところに見られて面白いです。この応接室だけでも、家紋なのかな?武田菱のようなマークが彫られていたり、ドアの上にはゼセッション的な模様が彫られているし、ひとつ言えることは、情報量が多すぎる!![]()
コロナが落ち着いたら館内ガイドやってくれないかしら。
さて、帳場は撮影しにくかったのですが、隙を狙って撮ってみました。

写真中央が玄関からダイレクトに入れるドア。その奥に畳敷の帳場が見えるでしょうか?
玄関から入ってきた重要なお客様が、履物を脱いで帳場を通って応接間に入るのではなく、玄関からそのまま入ってこられる。まさに和と洋の良いところや利便性を突き詰めたおうちです。
そして応接室の横には外に出られる通用口もあります。

お客さんはここから出入りすることはないだろう。と、油断していたら。

素敵なステンドグラスが。正面の入口の柵のとこから見えました!
床もおしゃれだな。
でも、不思議なことにこの建物で(公開しているところで)ステンドグラスがあったのはこの場所のみ。住んでいる人にとっての装飾というよりも、外から見せるための装飾だったのでしょうか。
いわゆる、「見せステンドグラス」的な!?![]()
中庭のようになっていたので外に出てみた。
外から見たらやっぱりすごかった。

ステンドグラスがあるスペースはとても明るかったのですが納得。外から見たら窓がたくさんあった。そりゃ明るいわけだ。
さらに出口の上にはステンドグラスがあったスペースの床と同じ模様が。おいおい、凝ってるな。
そしてバルコニーのようなものも。2階の書斎から出られるバルコニーのようです。
そういえば、明治から大正初期の洋館ならエントランスの上にバルコニーがあってもおかしくないけど、逆に無いところが大正モダンという感じでよい!

そして不思議なことが、「洋」の出口に対し、狛犬が!ちょっとうつむき加減なところがかわいい。
そういや、確か旧朝香宮邸(東京都庭園美術館)にも洋館なのにエントランスには狛犬がいたな。
こんなところで和洋折衷。

ゼセッションの幾何学的な模様が装飾されたところがここにも。
実はこの突き出た部分、「蔵」なんです。「内蔵(うちぐら)だそうで、あえて蔵造りにしなかったのは、レンガで作られて耐久性も良いからということなのでしょう。
実際、関東大震災でも崩れなかったという。明治初期のレンガ造りの建物は、関東大震災でその多くが崩れたそうだけど、洋風に見せつつ、地震の多い日本の建築技術を実地で学んだ櫻井ならではの設計だったのかもしれません。

文庫蔵(旧仕込み蔵)。これも国の重要文化財の建物です。非公開です。
この写真の左側に通用口があり、ここから作った味噌や荷物を運んでいる絵が3Fの蔵の中の資料室にありました。「庭」かと思ったら、通用口だったという。どんだけ旧田中家住宅、広いんだ!
3階編に続く
![]()
「和洋折衷のいいとこ取り!旧田中家住宅 INDEX
- (1)和洋折衷 とにかく凝った洋館なのです
- (2)素敵な階段室から3階の内蔵と控えの間へ
- (3)超ゴージャスな大広間は必見!
- (4)和洋折衷を体感するなら和室を見よう!
- (5)池泉回遊式庭園と茶室を見学
![]()
ぽちっとひと押し。応援お願いします♪